インターンシップの選考で必ず求められる「自己PR」ですが、「何をどう書けばいいかわからない」「自信を持てるエピソードがない」と悩む学生も多いのではないでしょうか。
自己PRは、特別な実績がなくてもあなたの考え方や行動から“らしさ”を伝えることで十分に評価される項目です。
本記事では、自己PRの本質や探し方、タイプ別の表現方法、企業が評価するポイント、そして実際の例文までを丁寧に解説していきます。ぜひ自己PR作成の参考にしてください。
自己PRって「何を伝えるもの」なの?

「そもそも自己PRって、何を伝えるのが正解なの?」という方も多いでしょう。まずは自己PRの本質を理解し、自分らしさを言葉にすることが重要です。
スキル・成果よりも“らしさ”が伝わるかどうかが大事
インターンで求められるのは、即戦力となるような完璧なスキルではなく、「どんな姿勢で学ぶか」「どんな考えで動くか」といった人柄や行動スタンスであるため、選考担当者が自己PRから見たいのは、その人らしさや誠実さ、成長意欲です。
たとえ大きな実績がなくても、自分なりに工夫して取り組んだ経験や、周囲とどのように関わってきたかを丁寧に伝えることで、好印象を与えることができるでしょう。
「自分らしさ」の伝え方は1つじゃない
「リーダー経験がない」「表彰されたことがない」といった不安を持つ学生の多くが、工夫次第で伝え方はいくらでもあるということに気付けていません。
日々の生活の中で、人のために動いた経験やコツコツと続けた習慣など、小さな努力や心がけこそがその人らしさです。「授業の中で工夫したこと」「友人関係で意識していること」なども立派なPR素材になります。目立つ成果だけにこだわらず、自分らしさの表現方法を探してみましょう。
「意識してきたこと・行動の癖」がヒントになる
「私は何もアピールできることがない」と感じている学生であっても、自分が当たり前のようにやっていることの中に、他人には真似できない“強みの種”が隠れています。
例えば、「提出期限は必ず守る」「相手の顔色を見て声をかける」「誰よりも早く資料を準備する」など、無意識の行動の癖を洗い出してみると、自分の特徴が見えてくるでしょう。これまでの自分の行動パターンに共通する“無意識の習慣”が必ずあるはずです。
自己PRと志望動機の違いとは?
「自己PR」と「志望動機」は混同しやすい項目ですが、実はまったく役割が異なります。
前者は“あなた自身”の魅力を語る内容(どんな人なのか、どんな強みがあるのか)であるのに対し、後者は“企業との接点”や“共感した理由”を語る内容(なぜこのインターンを選んだのか)です。
選考でこの2つが混ざってしまうと焦点がぼやけるので、それぞれの目的を意識して明確に書き分けましょう。
自己PRネタを見つけるための「4つの視点」
ここでは、「自己PRに使えるような経験がない…」と感じている学生のために、自身の強みを見つけ出すための4つの視点をご紹介します。
小さな成功体験を思い出す
「成功体験」と聞くと、表彰歴やリーダー経験を思い浮かべる方が多いですが、自己PRに必要なのは“大きな成果”ではなく、“自分なりに工夫してうまくいった経験”です。
例えば、「ゼミの発表で、スライドの構成を工夫して伝わりやすくした」「部活動で後輩をサポートした結果、チームの雰囲気が良くなった」といった小さな成功も立派なPR材料になります。特に「どんな課題があり、どう乗り越えたか」が伝われば、評価につながるポイントになるでしょう。
周りの友人や先生に聞いてみる
自己分析が苦手な方におすすめなのが、他人の目を借りることです。自分では当たり前すぎて気づいていない強みも、友人や先生など身近な人から見れば「魅力」として伝わっていることがあります。「いつも丁寧だよね」「安心して任せられる」と言われたことがあれば、それは立派な評価の1つといえるため、言葉の背景にあるエピソードをしっかりと掘り下げることで、自分らしさをより客観的に伝える自己PRが完成するでしょう。
「困った状況で自分がした行動」を振り返る
人はピンチのときに本質が表れるものです。自己PRにおいても、困難な状況で「どんな行動をとったか」「どう考えて動いたか」は、その人の価値観や強みを表現する格好の材料になります。
例えば、「グループワークがうまくいかず、意見の食い違いが起きたとき、自分から話し合いを提案した」「スケジュールが遅れていた企画を、自分のアイデアで立て直した」など、課題解決に向けての行動は評価されやすいポイントになるでしょう。
「なぜそれが自分の強みだと言えるのか」を問い直す
「私は責任感があります」「協調性があります」といった強みをそのまま書くのは、少し弱い印象になります。本当に伝えるべきなのは、“その強みを裏付ける行動や経験”です。「なぜそう言えるのか?」という問いを自分に投げかけ、実際にその力を発揮したエピソードを添えましょう。
例えば「グループの進行役を最後までやり遂げた経験」や「苦手な相手にも誠実に対応した経験」があれば、それがあなたの“強みの証拠”になります。
タイプ別!自己PRの切り口アイデア集

自分の強みをどう表現するかに悩んだら、あなたの性格や行動に合った切り口を考えてみましょう。自己PRが一気に書きやすくなるはずです。
協調性タイプのPRポイントと表現例
周囲との連携を大切にしてきた経験がある方は、チームワークやサポート役としての行動を強みとしてアピールしましょう。目立った成果がなくても、仲間を支えたことや、トラブル時に冷静に対応した姿勢などは立派な自己PRになります。例えば「グループでの作業において、相手の意見を尊重しながら意見をまとめた」「困っている友人に声をかけてフォローした」といった経験から、自分の“周囲を見て動ける力”を伝えるのがおすすめです。
行動力・挑戦タイプのPRポイントと表現例
新しいことに挑戦した経験や、誰よりも早く行動に移したエピソードがある方は、その「勢い」と「決断力」が強みになります。ただし、“やってみた”だけで終わらず、その行動がどういった影響や結果を生んだかまで言及しましょう。
例えば、「人前で話すのが苦手だったが、プレゼンのリーダーに立候補して乗り越えた」「思い切って未経験のアルバイトに飛び込み、結果的に月間MVPを獲得した」など、行動の裏にある思考や目的を加えられると説得力が増します。
継続力・地道タイプのPRポイントと表現例
大きな成果はなくても、日々の積み重ねを大切にしてきた方は、その“継続力”をアピールできます。特に、コツコツ努力したことで周囲に良い影響を与えたエピソードがあると評価されやすいです。
例えば「毎日英単語を30個ずつ覚え続けた結果、模試で偏差値が10上がった」「半年間続けたボランティア活動で、信頼される存在になった」など、過程を大切にしていることが伝わる書き方を意識しましょう。“派手さはないけれど確実に積み上げる力”はどの業種でも重宝されます。
計画性・分析力タイプのPRポイントと表現例
「物事を順序立てて考える」「事前に準備を重ねて臨む」といった特性は、計画性や分析力として強みになります。インターンでは“行動の根拠”を持って動ける人が評価されるため、準備力や問題解決の視点をうまく表現するとよいでしょう。
例えば「定期テストに向けて3か月前から学習計画を立て、効率的に勉強できた」「サークルの活動がうまくいかない原因を分析し、改善案を提案した」など、工夫したプロセスや検証の結果を伝えることが重要です。
企業が“いいな”と思う自己PRの共通点とは?
企業が「この学生いいな」と感じる自己PRには、共通点があります。ここでは、その代表的な3つのポイントを紹介します。
スキルよりも“再現性”があること
企業がインターンの自己PRで見ているのは、目立つスキルや成果そのものではなく、「この学生の強みは他の環境でも発揮されそうか?」という“再現性”です。
例えば、「学園祭でリーダーを務めた」という実績があっても、それがたまたまの成功では意味がありません。強みが再現性を持つためには、どのような場面でその力が発揮されたのか、その背景にある考え方や行動パターンを言語化することが大切です。「自分はこういう状況でこう動く人間だ」と伝えることで、相手は「この人なら職場でも同じように動いてくれそう」とイメージできるでしょう。
再現性の高い自己PRは、インターンのような“実践の場”では特に重視されやすいポイントです。
「その人らしさ」が文章ににじみ出ていること
多くの学生が似たようなフレーズ(「粘り強く取り組みました」「積極的に挑戦しました」など)を使う中で、印象に残るのは“その人にしか書けない言葉”です。
例えば、単にリーダー経験といっても、「どんな人とどんな関係を築いたか」「自分なりに何を意識していたか」など、背景の描写にその人の価値観や人柄がにじんで見えるような内容のほうが望ましいでしょう。また、行動の動機や感じたことを添えると、よりリアルな自己PRになるはずです。
「すごいことをしたかどうか」よりも、「その経験をどう受け止めてきたか」「どんな自分になろうとしてきたか」といった視点が、読み手の記憶に残る自己PRをつくる鍵になります。
「読み手の知りたいこと」に沿っていること
自己PRでは、“自分が言いたいこと”だけを優先しすぎないことが大切です。読み手である企業が「この学生はうちのインターンで活躍してくれそうか?」「どんな価値観・姿勢を持っているのか?」といった視点で読んでいることを理解しましょう。
例えば、教育系の企業であれば「子どもや人の成長に関心があること」、企画系のインターンであれば「仮説を立てて考える力」などを求められる傾向があり、そうした視点を意識すれば、同じ経験でもどこを強調すればいいかが見えてきます。
自己PRは“発表”ではなく“会話”であることを意識し、相手が知りたいことに自分の経験・強みを使って“どう答えるか”が、伝わる自己PRへの第一歩となるでしょう。
実際に選考を通過した自己PR例文3選
ここからは、実際に当社のインターン選考を通過した自己PR文を3つご紹介します。ぜひ書き方の参考にしてみてください。
(パターン①)リーダー経験はないけど頑張った学生の自己PR例
私は「チームが安心して動けるように全体を支える力」があると自負しています。
これまで目立つ役職に就いた経験こそありませんが、裏方として誰かの挑戦を支えることに大きなやりがいを感じ、大学のゼミではプレゼンの原稿作成やスライドの構成チェック、資料整理など、目立たないけれど欠かせない作業を率先して引き受けてきました。発表当日は登壇しませんでしたが、「この資料があったから自信が持てた」と仲間に言ってもらえたことが、何より嬉しい経験でした。
さらに、スケジュールの遅れが発生した際には、自らタスク管理表を作成し、プロジェクトの進行を立て直す工夫を行いました。
このように、私は常にチーム全体の状況を見ながら自分にできることを考えて行動する姿勢を大切にしており、こうした経験から、チームの土台を整え、周囲が力を発揮しやすい環境をつくる“縁の下の力持ち”として、今後も周囲を前向きに動かせる存在でありたいです。
(パターン②)苦手を克服したエピソードがある学生の自己PR例
私の強みは、「苦手でも逃げずに努力を続ける力」です。
つい数年前までは、人前で話すことに強い苦手意識がありましたが、大学の授業でプレゼン発表の機会が増えたことをきっかけに、「伝える力を身につけたい」と考えるようになりました。最初は原稿を読むだけで精一杯でしたが、話す内容を自分の言葉で表現し、事前に友人に聞いてもらうなどの工夫を重ねる中で、徐々に周囲の反応が見えるようになり、発表への緊張も和らいでいきました。ゼミ内の最終発表では「一番わかりやすかった」と評価され、自信を持つことができました。
この経験を通じて、自分は苦手なことを継続的な努力で乗り越えられるタイプであると気づきました。現在も、発信力をさらに高めたいという思いから、少人数のディスカッションに積極的に参加するなど、小さな挑戦を続けています。貴社でも課題から逃げることなく、試行錯誤を重ねながら前向きに成長していきたいと考えています。
(パターン③)小さな変化に気づける学生の自己PR例
私は、人の変化や感情の動きに敏感なことが強みだと考えています。
学生時代、学習支援ボランティアとして小学生の学習サポートを行っていた際、いつもは元気な子が静かにしていたことに気づき、「今日は何かあったの?」と声をかけました。話を聞いてみると、友人関係で悩んでいたことがわかり、その後も様子を見ながら丁寧に接するように心がけたことで、次第にその子の表情が明るくなり、学習にも前向きに取り組めるようになりました。
この出来事から、「相手に寄り添い、信頼関係を築く力」が自分の強みであると感じました。他の子どもたちに対しても、無理に声をかけるのではなく、相手の反応に応じて距離感を調整するよう心がけてきたため、決して目立つ役割ではないかもしれませんが、些細な変化に気づいて相手の気持ちを尊重できることは、どんな環境でも活かせる力だと信じています。今後も“気づく力”を大切に、人との関わりを深めていきたいです。
まとめ
インターンシップの自己PRは、自分の“強み”をただ並べるだけではなく、「どんな行動をとってきたか」「その強みがどう活きるか」までを具体的に伝えることが重要です。
企業は、スキルそのものよりも、その人らしさや再現性、そして目的意識を重視しています。目立つ経験がなくても、自分らしい視点で取り組んできたことを丁寧に言語化すれば、魅力ある自己PRになります。
今回の内容を参考に、自分の経験を改めて振り返り、企業に伝わる“あなただけの自己PR”をぜひ作ってみてください。


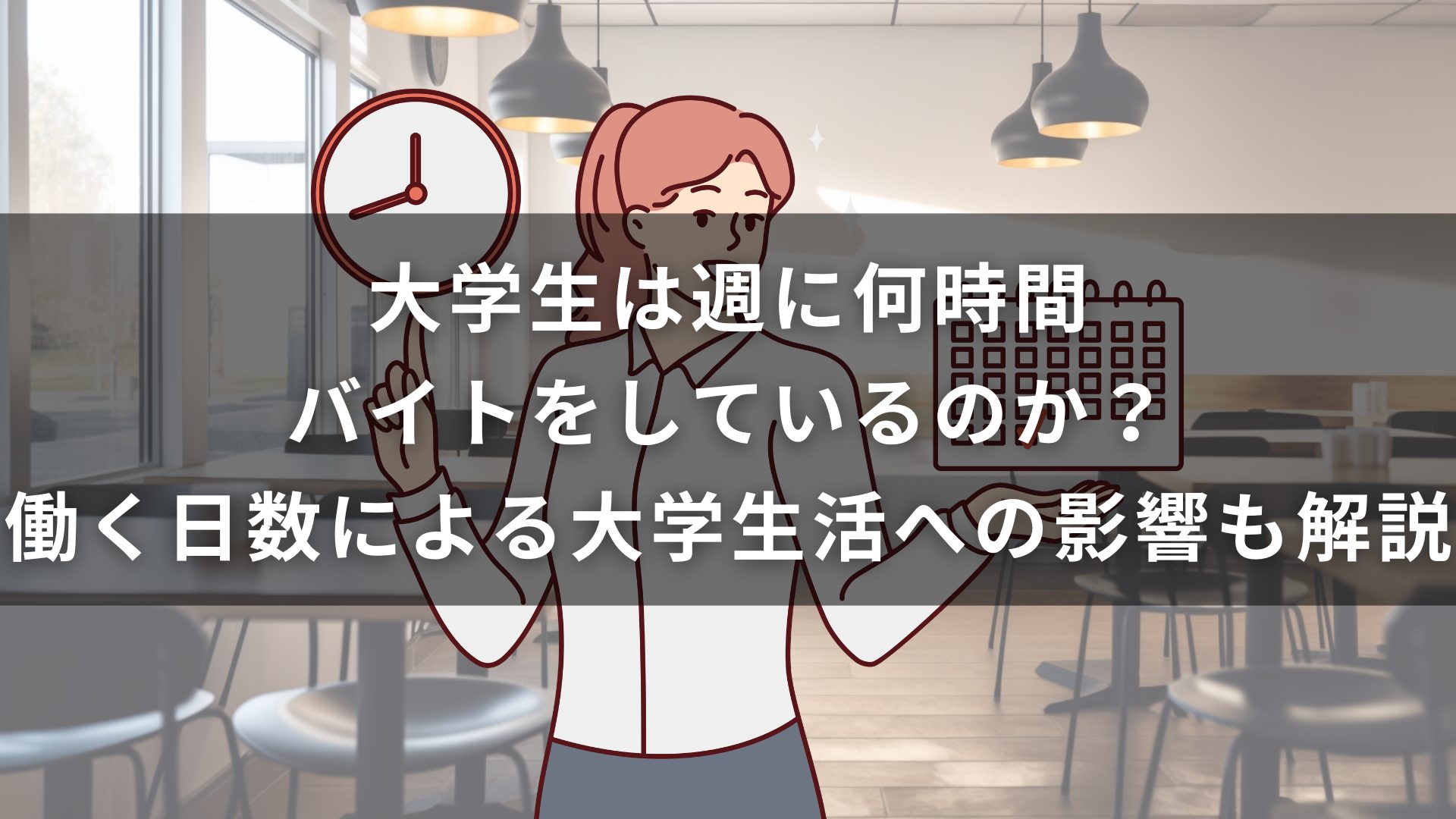
コメント